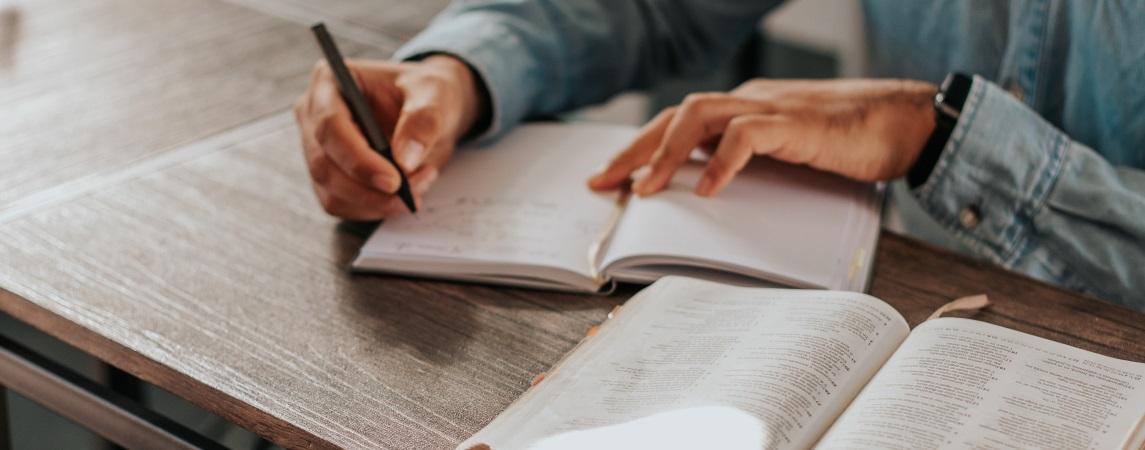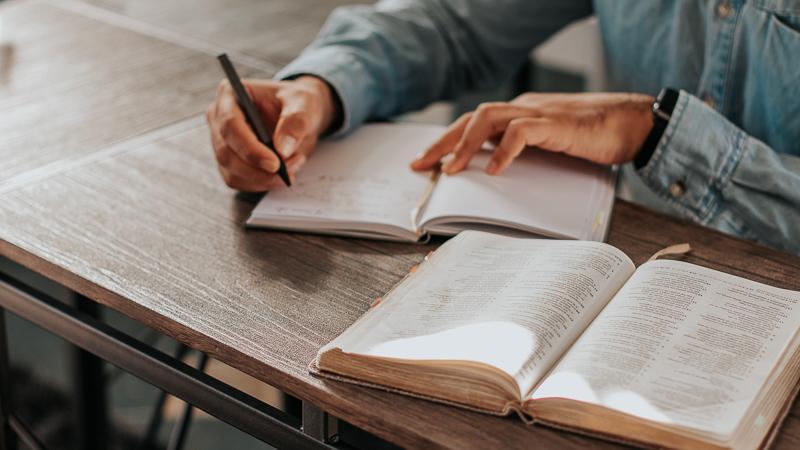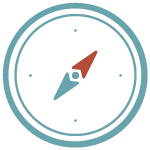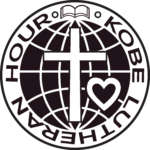西日本福音ルーテル教会のホームページへようこそ。
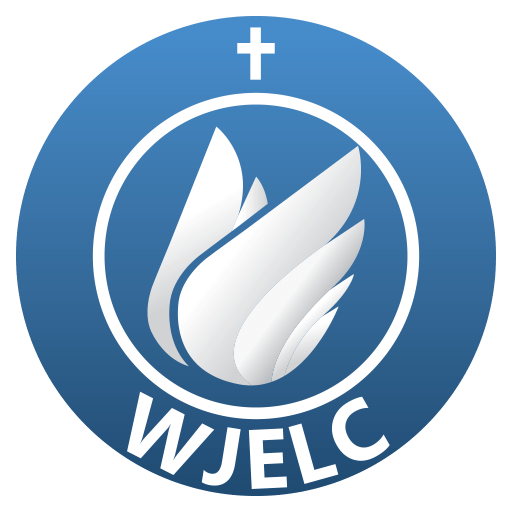
私たち西日本福音ルーテル教会は、神の愛と恵みにより、救われた喜びに共に歩んでいます。
そして礼拝は、イエス・キリストから罪の赦しが宣言され、新たに生きる力が与えられる場所です。
その「喜びのおとずれ」の礼拝に一緒に参加され、ご一緒に幸いな人生を歩むことができるようにと願っています。
どうぞお近くの西日本福音ルーテル教会へお尋ねください。
その入り口として、このホームページがあなたのお役に立ちますよう、そして、愛と恵みに満ちた神の祝福があなたにありますように。



神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。
独り子を信じる者が一人も滅びないで、
永遠の命を得るためである。
— 新約聖書 ヨハネによる福音書3章16節 —
私たちの活動
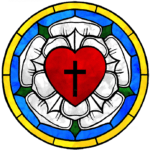
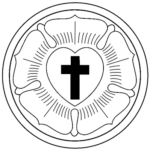

情報掲示板
01
04 '24
主題聖句
「見よ、主は御目を注がれる、主を畏れる人、主の慈しみを待ち望む人に。」詩篇33篇18節
活動方針
以下の取り組みについて、教会全体で互いに助け合い、サポート、推進してまいります。
1.地方教会の福音宣教
2.青少年活動、および宣教団体との協力